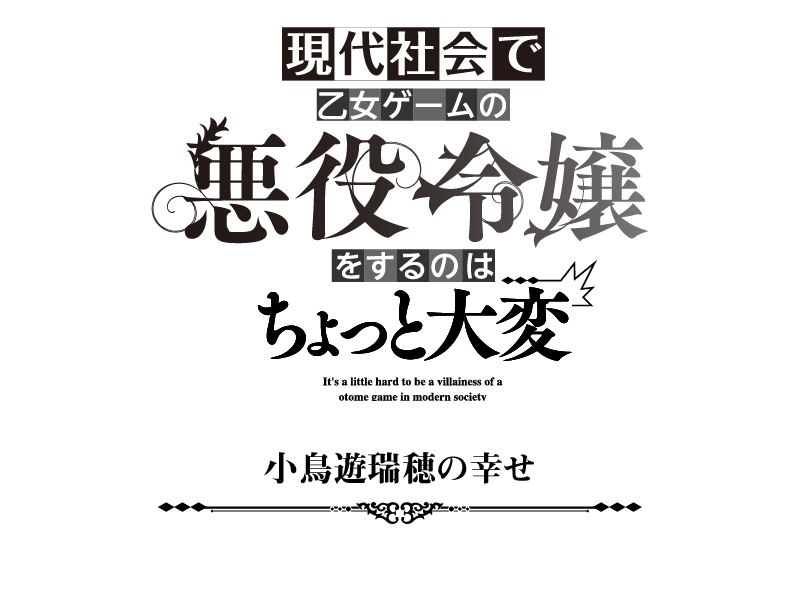私は、きっと幸せなのだろう。
今日の幸せが、明日も続くと思っていたのだから。
「瑞穂。瑞穂って名前はどうだろうか?」
「素敵ね。いつか、名前の通りの景色をこの子に見せてあげたいわ」
私が生まれた時、両親はそんな事を言ったという。
父はフリーの記者時代に専門学校に通っていた母と知り合い、今は母の夢である喫茶店でマスターをしている。
母は喫茶店で料理やお菓子作りの傍ら、料理教室をしたりして地域のママさんたちと楽しく話をする姿をよく見る。
そんな喫茶店の名前は『千歳縁(ちとせえにし)』。
和色の千歳緑の書き間違いからなのだが、母が気に入ってこの名前になったとか。
店はパートの人三人を雇って今日も営業しているが、父は時折断れない仕事で記者の仕事を手伝うこともある。
生活は苦しくなかったが、かといって苦しい時期が無い訳ではなかった。
私が小学生に入る前か入ったあたりが一番きつかったような記憶がある。
喫茶店ではなく記者の仕事で父が帰るのが遅くなり、母が一人で喫茶店を回していたぐらいだろうか。
世間が災害や事件で妙に暗かったのを覚えている。
父と母が喧嘩する事もあった。
ただ、それも弟ができた事で仲が元に戻ったのだが。
あれは何時だっただろうか?
両親と共に川岸を散歩した時だったと思う。
川向こうに日が落ちてゆく景色が綺麗で、なぜか涙が出たのだ。
その時に、父は私を抱いてこんなことを言った。
「涙をふきなさい。今日よりもきっと明日はもっと幸せになるのだからね」
明日は今日よりもきっと良くなる。
その言葉は黄昏色の景色と共に私の心に焼き付いた。
帰り道、私はその人を見つける。
『――欲しい物はありましたか? 小さな女王様』
「きれい」
それは当時近くのスーパーに張られたポスターだったと思う。
『小さな女王様』桂華院瑠奈を見た最初だったと思う。
大きな椅子に座って時計を見ているきれいなお姫様。
そんな思いが素直に言葉として「きれい」とこぼれたのだ。
だが、そのポスターを見た父は悲しそうな顔をしていた。
「そうだね。きれいだね。けど、彼女は知っているのかな? そのきれいにどれだけの代償があったかという事を」
父の言葉は小さく低く重たかった。
ぞくりという悪寒に父は慌てて記者の顔でなく父の顔に戻る。
「すまないね。瑞穂。忘れてくれると嬉しいな」
その言葉を忘れることができなかったのは、私の罪なのだろうか?
それとも、父の願いだったのだろうか?
このポスターから桂華院瑠奈という名前は世間に確実に広がってゆく。
同年代の女子達は彼女のおしゃれを真似、大人たちは彼女につけられたニュースに夢中になった。
「桂華グループのムーンライトファンドの持ち主があのお嬢様なんだって」
「若くして億万長者なんですって。羨ましいですわね」
「しかも、桂華院公爵家の血だけでなく、ロシア帝国の皇室の血を引いていらっしゃるとか」
「子供モデルとしても活躍しているし、オペラ歌手としてデビューするとか」
母の手伝いで喫茶店に入る時、集まっていたママさんたちも彼女の話題を口にした。
母はカウンターの向こうでママさんたちの話に適当に相槌を打ちながら、私の皿洗いを見て微笑む。
つけられたテレビは、不良債権処理に伴う社会の停滞と政治の迷走をニュースが非難していた。
「一体いつになったら景気が戻るのかしらね?」
「リストラとかも増えたわよね。うちの旦那は大丈夫かしら?」
「政治がしっかりしていないからよ。私達もいい加減にNOを突きつけなきゃ」
母はいつものようにカウンターで作業をする。
けど、そういう話題を嫌うことなく私に聞かせるままにしてくれた。
お店を閉めて、喫茶店の奥の家に戻る時に母はこんな事を聞いてきた。
「ねぇ。瑞穂ちゃん。大きくなったら何になりたい?」
「うーんとね。桂華院瑠奈ちゃんみたいなお姫様!」
その時の私の言葉を母は笑わなかった。
だが、その時の母の言葉は覚えている。
「そうね。きっと貴方ならなれるわ。お姫様でも、それ以上でも。さあ。晩御飯は瑞穂の大好きなカレーライスよ」
「わーい♪」
だから私は頑張るのだ。
お姫様になれるように。
それ以上になれるように。
「姉ちゃんがお嬢様になんかなれる訳ねーじゃん!」
「なれるもん!」
弟とはよくそんな喧嘩をした。
あの頃から桂華院瑠奈は私達女の子の憧れだったのだ。
慣れないおしゃれや流行に乗って弟にからかわれてあとはよくあるパターンだ。
もちろん、私が本当に桂華院瑠奈みたいなお嬢様になれるとは思っていない。
サンタクロースの正体が父や母だったというぐらいには現実を理解していたが、かといって憧れと流行から背を向けられる訳もなく。
「あんただって桂華院瑠奈みたいな彼女欲しいくせに!」
「姉ちゃんそれ言ったらだめだろうが!!」
弟とて男の子である。
かわいい彼女が欲しくない訳がない。
かくして、よくある口喧嘩は両方とも疲れ果てていつの間にか終わるのだ。
「姉ちゃん好きな男子とかいねーのかよ?」
「いないわね」
「なんかもったいねーな」
いつの喧嘩だったか、そんな事を弟が言ってきた。
多分弟なりの褒め言葉だったのだろう。
「きっと姉ちゃんはいい男子を捕まえるよ。桂華院瑠奈みたいに」
「え? 桂華院瑠奈って彼氏居たっけ?」
「知らない。けど、居ないとおかしーだろ。あの桂華院瑠奈だぜ」
「そりゃそうよね。桂華院瑠奈の彼氏みたいな人を私も見つけられるかしら?」
「そりゃ、桂華院瑠奈でも結婚するなら一人だし。という事は、その人以外は空くって事だろ?」
弟のその言葉は天啓だったと今でも思う。
ハイエナといえば聞こえが悪いが、その時の私は、桂華院瑠奈でも結婚するなら一人の男子しか捕まえられないという当たり前の事実を噛み締めていたのだ。
つまり、彼女の周りを取り巻く麗しの貴公子たちの一人を捕まえられるかもと思ってしまったのだ。
「どうやったら捕まえられるかな?」
「そりゃ、桂華院瑠奈と同じ学校に行けば捕まえられるんじゃね?」
その言葉がなければ調べなかっただろう。
桂華院瑠奈が通っている帝都学習館学園への入学方法を。
華族や財閥の御用達の学園に特待生という制度があるという事を。
私はきっと幸せだったのだろう。
私はこの時、私の幸せだけを考えていれば良かった。
彼女が、桂華院瑠奈さんがこの時何をしていたのか、何をしようとしているのか知らなかったのだから。