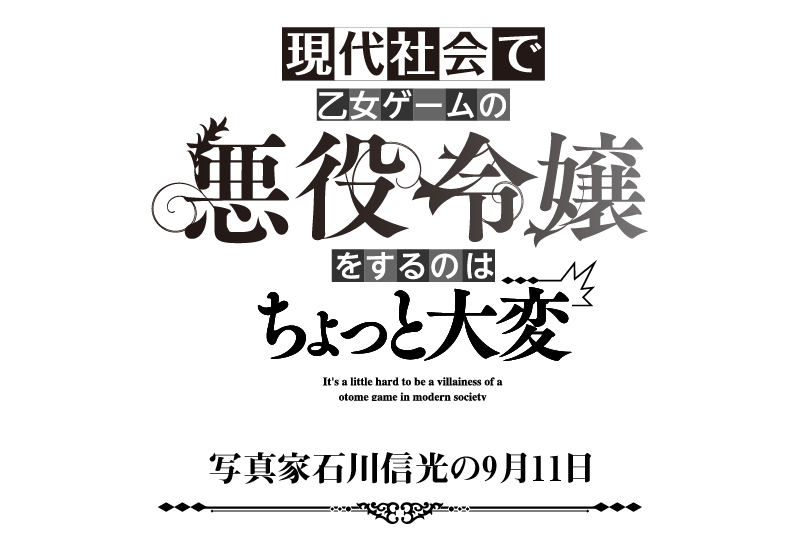写真家石川信光が九段下桂華タワーのパーティーから帰ったのは日を跨ぐかというあたりだった。
テレビは崩壊したツインタワーの映像と、混乱する米国の情報をまるで映画のように伝えていた。
冷蔵庫を開けてビールを取り出して、開けることなく冷蔵庫に戻す。
悪い夢なら覚めてくれと思ったが、この現実が覚める事はなく、テレビの特番は同じ情報を繰り返すばかり。
「そうだ。現像しないと」
彼はカメラマンだった。
彼が生涯をかけて撮りたいと思った被写体である桂華院瑠奈の晴れ舞台だった九段下桂華タワーのパーティーの写真を撮りに行っていたのである。
フィルムを持って現像室に入る。
そして、彼にとっての9月11日は始まった。
「原稿は全部差し替えろ! 総理官邸、外務省、米国大使館に人間を送り込め!! 米国在住者にとにかく電話をかけて情報を引っ張り出せ!!」
「首都圏を中心に警察・自衛隊・警備員が警備と交通規制をかけています! 成田空港と羽田空港、関西国際空港は閉鎖が決定!!」
「警視庁と自衛隊にも記者を派遣しろ!! 専門家は確保できたのか!?」
「駄目です! 使える人間はテレビに引っ張られ、次に新聞に持っていかれました!!」
「この際誰でもいい! 知っている人間が居たらとにかく引っ張れ!」
鳴り止まない電話。
つけられたままの複数のテレビモニターには必ずどれかには崩壊するツインタワーが映っており、記者たちの怒号と出入りは深夜なのにひっきりなしに続けられていた。
そんな中、出版社の三流ゴシップ誌のオフィスに石川信光は入る。
三流ゴシップ誌もこのニュースを、世界が変わった特ダネをモノにしようと全員を叩き起こして情報収集に走らせていた。
「ああ。石川さんか。見ての通り、今は修羅場でね。うちも原稿差し替えでこの有様さ」
「そりゃ大変ね。編集長居る?」
知り合いの記者は顔で編集長室の方に顔を向ける。
そこからの怒号がタイミングよくやってきた。
「馬鹿野郎! 俺たちの雑誌に堅い事実なんていらんだろうが!! そんなものは、堅い新聞やきちんとした週刊誌に任せてしまえ!! それがわかったら、とっととネタを集めてこい!!」
記者がそのまま肩をすくめて仕事に戻ると、石川信光は苦笑しつつ編集長室に入る。
開ききったドアを数回ノックしてやっと血走った編集長の視線を向けさせることに成功した。
「なんだ石川さんか。すまないが、アレのせいで原稿は差し替えだ。ヌードグラビアについてはまた……」
彼の言葉が止まったのは、石川信光が封筒を差し出したからだ。
その封筒の中に何が入っているのか分からない人間が雑誌編集長なんてやっている訳がない。
ひっつかむように封筒を受け取り、彼はその写真を見た。
倒れ込んだ桂華院瑠奈公爵令嬢を抱きかかえた恋住総一郎総理の写真を。
「……」
「……」
あれだけ騒がしい編集部も離れたように音が遠くなる。
長く感じる永遠に等しい数秒の後、石川信光は情けない顔で笑ってつぶやく。
「なぁ。これ、どうしたらいい?」
「出せ」
まるで迷子を叱るように編集長は低く穏やかな声で即答する。
本物を前にすると人は本性を露呈させる。
この写真は間違いなく本物のスクープだった。
編集長は今度は諭すように石川信光に告げる。
「これを世に出せ。それはお前の運命であり、きっと俺はこの運命を世に出す為にこの仕事をしていたんだ」
そのまま編集長は受話器を取る。
同じ出版社の、格上の週刊誌の編集長にだった。
「……もしもし、俺だ。スクープをくれてやる。……ああ。それ絡みだ。わかった。そっちのオフィスにすぐ行く」
受話器を置くと、編集長は石川信光の肩を叩く。
その顔は笑顔だった。
「あんたが一生をかけて撮りたいって言った娘。いずれ、上流階級という籠の中に消えちまう鳥だ。撮り続けたいならば、あんたもその籠が見れる場所に行かないと撮れなくなる。この写真はその切符だよ。俺は乗れないがな」
「編集長……」
「さぁ。行くぞ。偉くなっても、うちの雑誌の安い原稿料でグラビアを撮ってくれるならば十分だ!」
その写真は、この出版社のオピニオン誌の表紙を飾って飛ぶように売れ、写真家石川信光の名前を不動のものにした。
その後ピューリッツァー賞を受賞した後でも、彼はこの三流ゴシップ誌を忘れなかった。
休刊するまで彼はできる限りその三流ゴシップ誌のグラビアやヌード写真を撮り続けたのである。