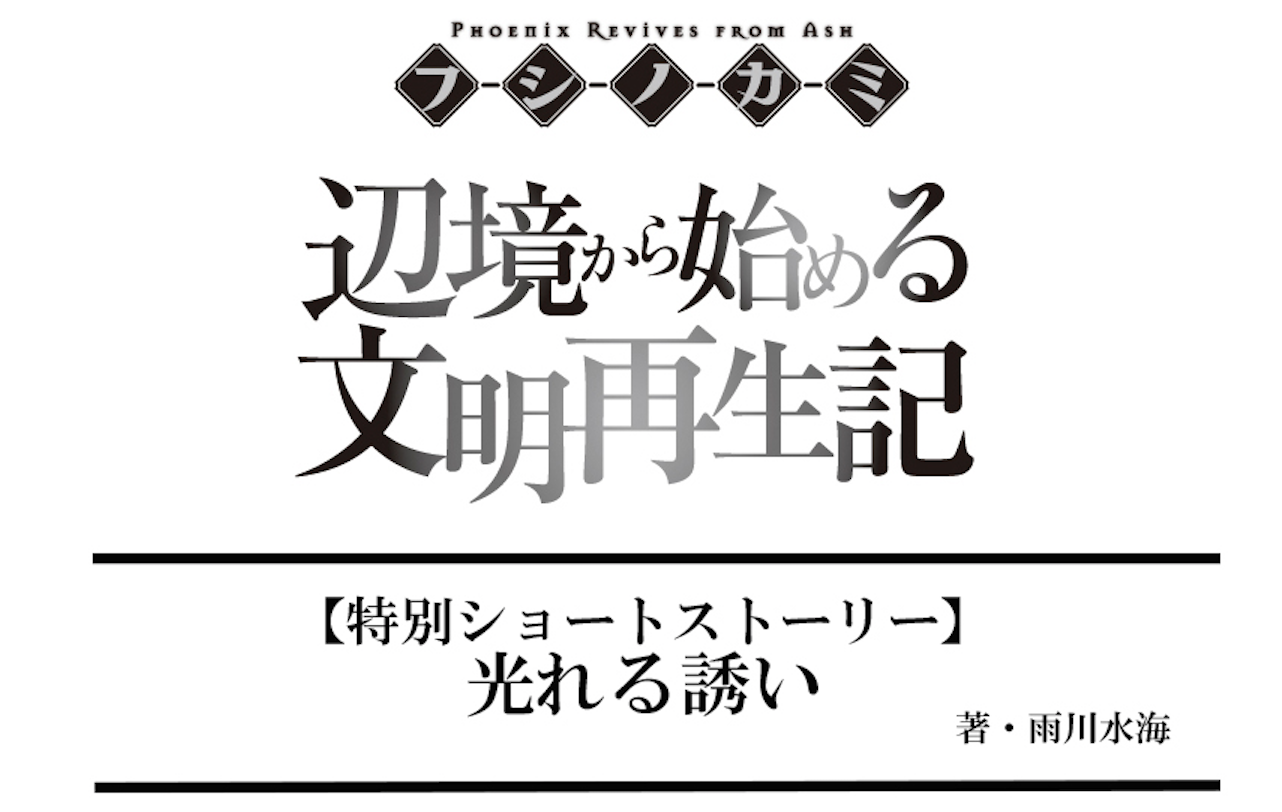その日は、珍しい休みだった。
朝食を終えた後、僕アーサーの同室であるアッシュが、いつもみたいに猛然と動き出さなかったのだ。
その、普段とまるで違う様子のせいだろうか。
少しぬるい夏の風が吹きこむ室内。頬杖を突いて本を読むアッシュの姿は、時折紙をめくる以外は止まったように静謐で、絵画や彫刻のような、造り物めいた存在に見える。
少し、ドキドキしてしまう。
このまま本をめくる音がしなくなって、本当に造り物になってしまうのではないかと心配で。
それと、こうして見つめていると、本当に整った顔をしているんだなって、気づかされてしまって。
不意に、紙をめくる以外の動きを、アッシュが見せた。
顔を上げたアッシュが、僕の視線を真っ向から絡め取る。
「アーサーさん」
「う、うん? どうしたのかな、アッシュ?」
じっと見つめていたことに気づかれてしまっただろうか。いや、気づかれたって問題ないよ。うん、だって、じっとしているアッシュが珍しいんだから、それはもう、見てしまうよね。
「市壁、見に行きませんか?」
けれど、というべきか。やっぱり、というべきか。
僕の焦りなんてどこ吹く風、アッシュの言葉はいつも通りに予想外だ。
「し、市壁?」
「はい、ピクニックです」
この子は、本当に突然なにを言い出すのだろう。
なんだかよくわからないうちに、市壁ピクニックは決行された。
あの後、アッシュはさっきまでが嘘のように素早く動き出して、マイカとレイナに声をかけて――残念ながら、レイナは用事があってすでに出かけてしまっていた――厨房のヤック料理長に声をかけ、お弁当を作り上げた。
「おっべんと~、おっべんと~♪ ア~ッシュく~んの、おっべんと~♪」
それだけでもう、マイカは大はしゃぎだ。本当に、マイカはアッシュが大好きだね。隠しようもないくらい、というか、隠す気もないくらい、というか。
「それで、アッシュ。どうして市壁に行くの?」
「今日は良い天気ですから。市壁の上からの眺めは良いですし、そこでご飯を食べるのは気持ちよさそうじゃないですか」
シンプルな答えに、う~んと苦笑してしまう。
「それはそうだと思うけど、そんな理由で市壁の上に入れてくれるかな……」
「おや? 入れてくれないと思います?」
僕の呟きに、アッシュはにっこりと、どことなく凶暴さを含んだ良い笑顔を返してくる。
思わず、視線をマイカに移して確認してしまう。
「ああ、うん、たぶん、そうだと思う」
マイカが、ご機嫌だった顔に微量の困惑を交ぜて、僕の予感を肯定した。ご機嫌が九割九分で、困惑が一分くらいかな。
僕と違って、ほとんど気にしていないみたいだ。アッシュもアッシュだけど、マイカもどうかと思うよ。
アッシュは、都市防衛の重要軍事施設への立ち入りについて、ちょっと強引な手段を考えているみたいだ。
「アッシュ? 一応確認しておくけど、市壁に上がるためには、門番の衛兵に許可を取る必要があるよね?」
「そうですね。ジョルジュ卿の備品管理のお手伝いで何度か市壁にも登っていますから、知っていますよ」
「今回は、備品管理の必要もなにもないよね?」
「臨検、という言葉があります。臨時の点検、抜き打ちの検査です。補充したばかりの備品が乱暴に扱われたり、横領されていたら大変ですね?」
うん、それは大変だと僕も思うよ。思うんだけど、なんと言っていいか……。とにかく、絶対おかしいよね?
「流石だね、アッシュ君! その聞き方だと、それは大変だねってアッシュ君の言葉を認めるところから入っちゃうから、ダメって言いづらい!」
「ありがとうございます、マイカさん。でも、バラすの早いです。ほら、アーサーさんがすごく怒った顔になってしまいました。可愛いですね?」
かわっ――!?
「そ、そんなこと言っても、ご、誤魔化されないからね! そ、それに、そう! 僕は男の子なんだから、可愛いとかないよ!」
勢いよく叫んだせいで、顔が熱い。そう、叫ぶくらい怒っているから顔が熱いんだよ、今。
そんなに怒った顔の僕を前に、アッシュは平然としている。憎たらしいくらいだよ。
「男女関係なく、可愛い表情ってあると思いますよ? ねえ、マイカさん?」
「そうだね。アッシュ君も、ご飯食べてる時はとっても可愛い……えへへ、思い出しちゃった」
「まあ、面と向かって言われると恥ずかしいのは確かですけどね」
ふふふ、と爽やかに笑って、それじゃあ、とアッシュは歩き出す。
本当にもう、アッシュは、気軽に人をからかってくるんだから。礼儀正しいし、気配りもできるのに、どうしてこう僕のことを刺激してくるのか。困った人だよ。
僕が内心で怒っているうちに、門についた。……あ、止めるタイミングを失っちゃった。
「どうも、いつもお疲れ様です」
「お、アッシュ君か。今日はどうした。また囚人どものところか?」
当番の衛兵と、顔見知りだったらしい。まあ、毎日のように囚人のところへ行くため、出入りしている姿が目立つだろうから、当たり前か。
「いえ、今日は市壁の上に用事がありまして、よろしいですか?」
「上に? ええと……なにも聞いてなかったと思うけど、なんだっけ?」
「市壁の管理状況について、抜き打ち検査です。巡回をサボっていたり、弩砲の保管に手落ちがあった場合、ジョルジュ卿に報告してしまいますからね」
「おっと、そいつはおっかないな。今日は上の見張り担当じゃなくてよかったぜ」
ははは、と衛兵は笑って頷く。
それだけだった。当たり前のように階段の入り口へ向かうアッシュを止める気配がない。
堂々としたアッシュにマイカが続いて、そのマイカに腕を引っ張られる僕が続いても、止めない。
「上だと強い風が吹く時もあるから、気をつけてな~」
最後に、そう手を振って注意してくれただけだった。
「いやいや、待って待って、流石にまずいよ。怒られちゃうから」
階段を上がりながら、さっき通り過ぎた衛兵を気にして小声で止める。
「そうでしょうか?」
アッシュはやけに自信ありそうに微笑む。
「マイカさんも、そう思います?」
「う~ん? 大丈夫じゃないかな~と思うけど……」
マイカは、こめかみに指を当てて首を傾げる。
「アッシュ君はジョルジュさんのお手伝いしているでしょ? 市壁の管理状況が気になるのは、仕方ないことだね?」
「その通りです。ジョルジュ卿の副官見習いとして、軍事施設の瑕疵は見逃せません。有事の際に慌てても遅いのです」
「じゃあ、暇な時に確認しておかないとだね」
この二人は、本当に息がぴったりだなぁ。ちょっとうらやましいよ。
でもね、二人とも、流石にジョルジュ卿を言い訳にしたって、それはちょっとどころじゃなく苦しいと思うよ。
僕が二人から距離を取ろうとするけれど、マイカがするりと僕の腕を取って抱きついてくる。
「そ・れ・に~、あたしとアーサー君の二人がいて、叱れる人ってそんないないと思うよ? まず叔父上が叱れないんじゃないかな?」
「あぁ、それは、確かに……」
イツキ兄様、マイカのことを溺愛しているみたいだから……。
思わず頷いてしまってから、腕に密着してくる温かさに思いが至る。
「ちょっ、マ、マイカ、離れて! なんてことしてるの、はしたない!」
「あはは、ごめんごめん。アーサー君なら、これくらいは良いかなって思ったんだけどさ」
「ああ、姪と叔父ですもんねぇ」
のほほんとマイカとアッシュが笑うけど、それにしたって――いやいや、それだからこそ外聞が悪いよ!
「まあ、そういうわけで、見張りに見つかっても大して怒られませんよ。都市の防衛施設の問題点を確認するため、お休みを有意義に使いましょう」
「は~い! ささ、アーサー君も行こう」
「ちょっと、話は終わってないよ! マイカ、話を聞いて!」
僕が必死に抗議するけど、アッシュは先にぴょんぴょん登って行ってしまうし、マイカはその後に続いて僕をぐいぐい引っ張っていく。
この二人は、本当に、強引なんだから!
仕方なく、僕も階段を上がっていく。
一歩を踏み出す度、頬に触れる空気が、少しだけ変わる。
ああ、そうか。市壁の中、都市の底に沈んでいる空気とは新しさが違うんだ。
周りの建物と同じ高さまで来ると、髪に当たる日差しの強さも違う気がする。太陽の近くまで飛び上がったような錯覚。
そう気づくと、さっきまで自分がどんな場所にいたのだろうかと不思議に思う。
振り返ると、都市全体が、今僕がいる場所より暗がりに沈んでいるように見える。
おかしいな。それほど違いがあるとは思えないのに、都市の中にも光はきちんと差しこんでいるのに、今、この場所の方が明るいのは、どうしてだろう。
「ほらほら、アーサー君、はやくはやく!」
「あっ、わ、マイカ、そんなに引っ張らないで!」
「ダ~メ! アッシュ君に置いてかれちゃうよ!」
手を引かれて見上げた先、マイカと、さらにその先にいるアッシュの背は、今僕がいる場所より太陽に近いように見える。
目を細めてしまうほど、眩しくて、温かそうな光景。
その光の当たる場所が、あまりにも気持ちよさそうで、つい、気が変わってしまう。
「もう、仕方がないなぁ……」
マイカに手を引かれる力よりも、一歩分、前に踏み出す。
二人の強引さに負けての一歩じゃない。自分で選んでしまった一歩だ。
ああ、とっても悪いことをしている。こんなこと、本当はしちゃいけないのに。
背筋がぞくぞくする。胸がどきどきする。
いけないことをしているのに、楽しさがこみあげてくるのを感じる。
知らなかった。自分が、こんなにも悪い子だったなんて……。
市壁の上を、アッシュに先導されて歩く。
さっきから、ずっと胸が跳ねるように躍っている。王都にいた時は、どんなダンスを習ってもこんなに鼓動の音が騒がしいと思ったことはない。
左に顔を向ければ、いつもは見られない街の風景。立ち上る炊事の煙、大通りを行きかう人、大きく見える寮館、意外と小さく感じる神殿。
右に顔を向ければ、いつもは見られない外の風景。丘の下に広がる平原、畑で働く人、遠くへ流れていく川、その川のさらに遠くに、夏でも白い雪を乗せた山……。
王都で目にしてきたものとはまるで違う。ここが異郷なのだと押しつけてくるような景色の数々。
「え~と、白角の山があそこだから、ノスキュラ村はあの辺かな?」
マイカの呟きが聞こえて、同じ方向に視線を向ける。
「見えるの? マイカとアッシュの村」
「見えないかなーと思ったんだけど……」
「あそこにある丘で隠れてしまうので、ここから直接見るのは無理ですよ。途中にあった林も、この方角からは村を隠す配置だったと思います」
そっか、と二人に返した言葉は、我ながら残念そうな響きだった。
「なにもない村ですよ?」
そういうことじゃないんだよ。アッシュの台詞に、頬を膨らませたくなってしまう。
「そういうことじゃないんだよ、アッシュ君」
そしたら、マイカが頬を膨らませて代弁してくれた。
もっとも、言われたアッシュは、そうなんですか、と大して気にした風もない。これには、マイカと二人そろって頬を膨らませてしまう。
アッシュは、二人の視線の矢でぶすぶす刺されているのに、平気な顔で手元の本をめくっている。あれは、アッシュが自分であれこれ書きこんでいる研究用の記述本だ。
「ええっと、確かこの辺ではないかと……ああ、この辺りで間違いないようです。石の品質も良いですし、風化具合も一段と古めかしい」
この辺り? 周囲の市壁を見渡す。
確かに、一つ一つの石がきちんと形が整えられていて、大きさも立派だ。角も長い年月だけが作り上げられる丸みを帯びている。王都の古い屋敷に使われているような、上質で古い石材が、この辺りの市壁には使われている。
「アッシュは、これを見に来たかったのかな?」
「ええ、そうなんですよ。初代サキュラ辺境伯閣下が、ここの開拓に乗りこんだ時、最初に持ちこんだ石材がこの辺りに使われていると聞きまして、見学するのも一興かと」
「へえ、そうなんだ……」
サキュラ辺境伯の初代といえば、当時王位継承権も持つ貴種でありながら、豪傑として知られた人物だ。僕も逸話はよく知っている。中央では、悪口混じりではあったけれど……。
「この石の一つに、初代様が遺した言葉が刻まれている、という伝説があるんですよ。もし見つけられたら面白いなと思ったのですが……」
アッシュはあっちを見たり、こっちを見たり、壁から身を乗り出して見下ろしたりするけれど、流石にそれで見つからないと思うよ。
「やっぱり、パッと見られるところにはありませんね。そうですよね、これで見つかるなら、巡回の衛兵さん達が見つけていますよね」
うん、そうだと思う。アッシュもわかっていたんなら、そんなにがっかりしなくていいのに。
目に見えて肩を落とすアッシュに、苦笑する。ちょっとかわいそう、と思えるくらい。
はげましてあげようかな、なんてその肩に手を伸ばそうとしたのは、僕だけじゃない。マイカも同時に手を上げている。
マイカと二人、ちょっとびっくりして、でもお互いの気持ちが手に取るようにわかって、小さく笑うと――アッシュが復活していた。
「とすると、やはり露出している面ではなく、内面。石と石が重ねられる部分に刻んでいる可能性が高いわけですね」
そうすれば風化から免れるわけですし、とアッシュは手近な石をペシペシ叩きながら呟く。
「それを見つけようとするなら、この市壁を解体する必要があるわけですね? なるほど、解体……流石に中を見たいから、では解体できませんね。なにか適切かつ有意義な言い訳が必要です」
復活したアッシュは、なんか恐ろしいことを言い出した。
「そもそも、領都という割にこの都市が狭いわけですし、都市の拡張に伴う市壁の延長工事ということならいけそうですね。というか、これ以外に市壁を解体する言い訳はなさそうと言うべきか……」
そもそも、市壁の拡張なんて石材が貴重な近頃、ほとんど聞かない、王国的にも一大事業だよ……?
石材不足のせいで新しい都市の建造が行えないから、地方の大規模開拓計画がここサキュラ辺境伯領を最後に、ほとんどできていない。
「まあ、他に手段が思いつかない以上、それでいきましょう。都市の拡張と、それに伴う市壁の解体延長。そうすれば結果的に、とても気になる初代様のお言葉の調査ができますね」
やりましょう、とアッシュは力強く言った。
それはもう、やらないわけがない、と直感できるくらいの力強さだった。
「アッシュ、流石にそれはちょっと落ち着こう? とんでもないこと言ってるから、ね?」
「ああ、大丈夫ですよ。いきなり明日から始めるわけではありませんからね。まず、十分な石材の調達から考えないといけませんね。十年かかるか、二十年かかるか……私が死ぬ前に終わると良いのですが」
大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないよ。死んでも止まる気はない、って断言してるじゃない!
マイカ、助けてマイカ。僕一人だとやっぱりどうしようもないよ!
「アッシュ君、なんか大変なこと言い出したねぇ。なんでそんなに気になるの?」
「この領地の歴史を少し調べたら、大変面白い人物だったんですよ」
流石、マイカ! アッシュの意識が、危険な方向から少しだけそれた。
「その人がわざわざ石に刻んでまで遺した言葉は、さてはてどんなものだろうかと気になりまして」
「そうなの?」
「ええ。公爵家の嫡男に生まれ、王都で安穏と暮らせただろうに、新しい土地の開拓話が持ち上がったらすぐに手を挙げるような人です。大きな家にありがちな家督争いがあったので、それにうんざりしていた、という面もあるようですけどね」
アッシュの説明に、僕が頷く。ていうか、マイカ、どうして君が知らないのかな。君のご先祖のお話だよ?
「また逸話が多い方で、この土地に来るまでの道中に盗賊団を蹴散らして傘下に加えたとか、通りすがりの領主の娘に惚れられて押しかけられたとか、飛竜と激闘の末にその背に乗ったとか、猿神様から叡智を授かったとか……いやぁ、冒険譚の主人公ですねぇ」
最後は人狼の群れを相手に大立ち回りして、最後の一匹と相打ちになったらしいですよ。心臓を貫かれながら人狼の首を跳ねたんですって。
アッシュの説明に、あれ、と疑問が浮かぶ。
「そうだった? 僕が聞いた話だと、その群れを討伐して帰って来たけど、大怪我を負っていて、しばらくして亡くなったって聞いたけど……」
「いえ? こう、心臓をぐっさりやられて、私だけ死んでたまるか道連れにしてやる~って切り返したのをよく覚えています」
「そうなんだ? まあ、王都ではそういうところが和らげられて伝えられるから、そのせいかな?」
二人には言わないでおくけど、王都を始め中央では、辺境の文化は野蛮だなんだと難癖つけられるしね……。
それにしても、アッシュの口調で物語を伝えられると、アッシュ本人が経験してきたみたいに聞こえて違和感がすごいね。アッシュも同じ目に遭ったら、そういう切り返しをしそうだから余計に……。
「イツキ様を始め、文武の官僚の方々にも初代様は大変な人気のようですからね。逸話の数々を見たら、それも納得と言いますか。血沸き肉躍る内政モノでしたね!」
確かに、ジョルジュ卿も市壁を自慢していたし、ここで働く人達が、初代から続くサキュラ辺境伯領を敬愛しているというのは、よく伝わってくる。
「その初代様の調査にあたって適切な理由がつくなら、皆さんこぞって協力してくれるのではないでしょうか」
あ、話が、戻ってきちゃった……。
僕はひるんだけれど、マイカは流石だった。
「はい! アッシュ君、あたしお腹空いた!」
「おや、もうそんな時間ですか?」
アッシュが空を見上げると、太陽がもう真上に近い。
「そのようですね。では、せっかくですし、ここで初代様を忍びながら、美味しいご飯にしましょうか?」
よかった。アッシュの勢いがまたまたそれた。
やっぱりアッシュを抑えるには、僕よりマイカの方が――
「わ~い! アッシュ君のごっは~ん♪」
そう思いかけたけど、今の場合は、単純にマイカがお腹空いただけの気がしてきた。
う、う~ん、良いコンビなのは間違いないけど、はたで見ているとそこはかとなく不安な二人でもある。
アッシュの暴走をマイカが抑える、という姿はよく見るんだけど、時々二人そろって暴走することもあるわけで……。
ここは、僕がしっかりしないといけないってことだよね。
がんばろう。不安しかないけど……。
「アッシュ君、アッシュ君、なに作ったの? お肉の匂いはしてたけど?」
「ハンバーグサンドですよ。しかも、トマトソースで煮込んだスペシャルなやつです」
「ほんと!?」
「さらにさらに、ヤック料理長からのご好意でチーズまで頂きました。これぞ、トマトソース煮込みハンバーグチーズスペシャルサンドです!」
ト、トマトソース煮込みハンバーグチーズスペシャルサンド!?
な、なんて(美味しさが)強そうな名前なの……!
アッシュがカゴから取り出すスペシャルサンドを、ついじぃっと見つめてしまう。はしたない、のはわかっている。
だって、トマト、美味しかったんだもん。
イツキ兄様とリインが禁止して、食べさせてくれないの。アッシュがこっそり食べさせてくれなかったら、来年の夏までこんな美味しい物をお預けされてたんだよ? ひどいよね?
「はい、アーサーさん、どうぞ」
「あ、ありがとう!」
わぁ、すっごく美味しそう。白いパンに、トマトソースの赤、少し黄色のチーズに、焼き色のついた分厚いハンバーグ、完璧な色合いだよ。
ちょっと興奮しちゃって、受け取る時に力が入りすぎたら、あふれた肉汁がパンに染みこんでいく。その様子がまた、美味しい予感をかきたてる。
うぅ、口の中にじゅわって涎が……。
「ええと、こっちがマイカさんのですね」
「わ~い、ありがと~」
はしゃぐマイカの声に、ちらりと見れば、アッシュが取り出したのは間違いなくマイカ用のご飯だった。
大きいんだよ。僕の倍くらいある。
僕、小食ってほどじゃないと思うんだけどな……。王都ではそうだったんだけど、ここで食べるご飯が美味しいから、普通くらい食べるようになってるんだけど……。
でも、アッシュの作ってくれたこのスペシャルサンドなら、僕でもあれくらい食べられるかもしれない。
それくらい美味しそうだ。
「それでは、食べましょうか?」
うん、という返事は、僕とマイカでそろった。
「では、頂きます」
御馳走にかじりつくのは、三人同時。
美味しい、と笑うのも、三人同時。
眩しいお日様の下、香りの鮮やかな夏の風が飛んでいく。
この日、思い出の燭台に灯されたのは、とても楽しい夏の火だった。